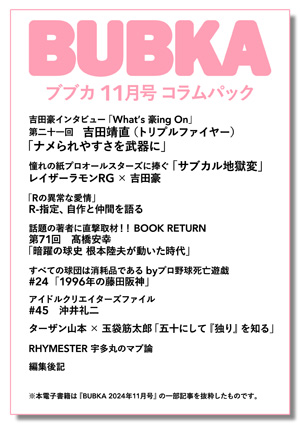不良少女から学んだ本当の意味でのつながり、比嘉健二著『特攻服少女と1825日』

ブブカがゲキ推しする“読んでほしい本”、その著者にインタビューする当企画。第58回は、第29回小学館ノンフィクション大賞を受賞した『特攻服少女と1825日』の著者である比嘉健二氏が登場。ヤンキー少女、レディースにフォーカスを当てた雑誌『ティーンズロード』を立ち上げた初代編集長が回想する、レディース文化の栄枯盛衰。ヤンキー少女よ、永遠なれ。
読者の6割は非ヤンキー
――本作は、比嘉さんが立ち上げた『ティーンズロード』の始まりと終わりを描いたノンフィクションです。創刊は1989年春。それ以前に、レディースを専門に扱う雑誌が存在していなかったことにも驚きました。
比嘉健二 もともと暴走族は、70年代中盤が最盛期でした。一つの場所にバイクが何千台も集まるような、今では信じられないような光景が広がっていて、その中にレディースもいました。大きなブームになっていましたから、二見書房やダイナミックセラーズ、第三書館といった出版社が暴走族を専門とした写真集をたくさん作っていた。特に、第三書館は『レディス』というタイトルの写真集を81年に発売しているんですよ。同時期に『ヤングオート』という改造車やバイクをメインに取り上げる雑誌が登場し、10万部近い売り上げを叩き出した。その影響もあって、『チャンプロード』や『ライダーコミック』といった類似雑誌が生まれていく……ですが、ヤンキー少女を専門に取り上げる媒体はなかったんですよ。僕は82年にミリオン出版に入社するのですが、そうしたヤンキー雑誌が好調であることを目の当たりにしていたから、ヤンキー少女やレディースに絞った雑誌を作れば売れると思ったんですよね。
――比嘉さんご自身は、そうしたヤンキー的な文化に対する素養はあったのでしょうか?
比嘉健二 抵抗感はなかったですね。といっても、まったく怖くないと言ったら嘘です。僕自身は暴走族ではなかったけど、ディスコが大好きだった。20代の頃に、新宿の東亜会館ビルの中にあるディスコなんかへ行くと、当時は暴走族とか不良のたまり場。矢沢永吉さんのキャロルも流行っていた頃で、僕も夢中になった。ヤンキー的な世界と、そう遠くないところで自分も青春時代を過ごしていたんですね。ですから、自分も出版社に入って成り上がってやる、出版業界を変えてやる――そうした気持ちを持って、ミリオン出版に入社したんだけど、最初に配属されたのがSMを専門に扱う『別冊S&Mスナイパー』(のちの『SMスピリッツ』)。それはそれで面白かったんだけど、売り上げ的には悪戦苦闘です。当時、白夜書房さんが『キングコング』というアダルト系雑誌を発売していたのですが、その雑誌も派手にコケていた。「(比嘉が作る雑誌は)白夜の『キングコング』の次に売れてない」ってよく言われていたなぁ(笑)。
――派手に失敗する時代!(笑)
比嘉健二 でも、図々しければ、また企画をすぐに出せる時代でもあった。そこで考え付いたのが、前述したヤンキー少女にフォーカスを当てた雑誌だった。当時は『ホットドッグプレス』がとても売れていたので、そのテイストにヤンキーカルチャーを少し混ぜたファッション誌のような雑誌を作ったら面白いんじゃないかなと思ったんですよ。あるとき、『URECCO』というセクシーグラビア雑誌の撮影で、三浦半島に行ったんです。その帰り道に、爆音で疾走するセダンのシャコタンを含む暴走族と遭遇したのですが、身を乗り出してハコ乗りしている少女がたくさんいた。おまけにルックスもかわいくて、垢抜けていた。一昔前のスケバンってスナックのママさんのように年季が入っていて、実年齢より上に見られそうな雰囲気があったのに、三浦半島で出会った少女たちは、アイドルのような華やかさがあった。この雰囲気を全面に押し出した雑誌を作ろうと思った。
――そうした流れの中で『ティーンズロード』の構想がふくらんでいったわけですね。
比嘉健二 当時って、『Popteen』もヤンキーを定期的に取り上げていたんですよ。加えて、先行雑誌である『ヤングオート』や『チャンプロード』の最後の方のページには、文通希望といったコーナーが設けられていた。よく見てみると、そこに投稿している多くが15歳くらいの少女たちでした。要するに、『Popteen』じゃ満足できないんですね。より真面目な『Seventeen』なんかは、もっと歯ごたえがない……ヤンキー的な世界にあこがれを持つ少女が潜在的に多い。ということは、この層を取り込むことができれば、絶対にヒットすると思いました。ですから、『ティーンズロード』第1号は「浦和レーシング」というレディースの女の子たちを表紙にした上で、アイドル雑誌『明星』をモチーフにして、女の子3人の表情を並べたんですよ。
――ところが、当初は売れずに苦戦してしまう。
比嘉健二 ポップな路線を意識し過ぎたあまり、ヤンキー少女特有の危険な雰囲気を出せなかったことに加え、書店に置かれたときに何の雑誌だが分かりづらかった(苦笑)。『ヤングオート』や『チャンプロード』は、改造車が表紙なので分かりやすい。一方、『ティーンズロード』は女の子がアップで映っているから、何系の雑誌か分からなくて、書店によってはアダルト系の棚に陳列されて
しまった。
――コンビニはどうだったのでしょうか?
比嘉健二 『ティーンズロード』って、一部のローソンでは置いてもらえたんですけど、ほとんどのコンビニはNGだったんですよ。置くと、購入したヤンキーたちがコンビニ前にたむろする可能性が高いから困るって(笑)。
――そんな理由が……。そうした状況を打破するのが、本書で描かれている東松山のレディース『紫優嬢(しゆうじょう)』をはじめとする個性的なヤンキー少女たちだったと。
比嘉健二 『紫優嬢』はビジュアルが良いことはもちろん、どこか危険な匂いがするチームだった。彼女たちを表紙にした第5号で方向性を掴んだことで、以降は出せばほぼ完売に近い数字をはじき出せるようになりました。印象的だった子たちとは今も交流が続いていて、今回この本を書くにあたっていろいろと事実確認もさせてもらいました。その中に、かつて豊橋に存在していた『三河遠州女番連合(みかわえんしゅうすけばんれんごう)』というレディースを率いていた伝説の不良少女・のぶこさんという方がいて、「あのときはこうでしたっけ?」という具合にいろいろと電話でお話したんですよ。「久しぶりに会えないですか?」と尋ねたところ、コロナ禍ということもあり「東京の人と会うのは怖い」と。怖いもの知らずだったのぶこさんを恐れさせるコロナは、すごいと思いましたね(笑)。
――コロナは、100人近いメンバーを引き連れていた女帝をもビビらせた(笑)。5号目以降は爆発的人気を集めていく『ティーンズロード』ですが、やはり購買層の多くは女性だったのでしょうか?
比嘉健二 ヤンキーの子が2割ほど、かわいいヤンキー少女を見たいという男性が同じく2割ほど、残りの6割がヤンキーでも優等生でもない、そうした世界にあこがれを持つような女の子でした。ヤンキー少女の総数って、最盛期でも全国で1万人もいないと思うんです。だけど、10万部も売れる。そういう世界に行き場を求めている読者が、かなりいたんだろうなと思います。
取材・文=我妻弘崇
――まだまだ続くインタビューは、発売中の「BUBKA10月号コラムパック」で!
比嘉健二|1956年生まれ。東京都足立区出身。1982年にミリオン出版に入社。『SMスピリッツ』などの編集を経て、『ティーンズロード』『GON!』などを立ち上げる。現在は、編集プロダクション『V1パブリッシング』代表。本作で第29回小学館ノンフィクション大賞を受賞。
【特攻服少女と1825日 Kindle版】
⇒ Amazonで購入

【BUBKA(ブブカ) コラムパック 2023年10月号 [雑誌] Kindle版】
⇒ Amazonで購入