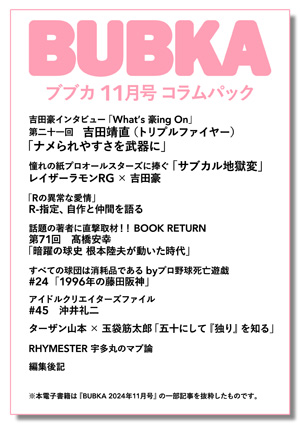清原和博が野球人としてもっとも輝いていた時代を読む3~プロ野球死亡遊戯があえて“令和の夏”に書きたかった話(著/中溝康隆)
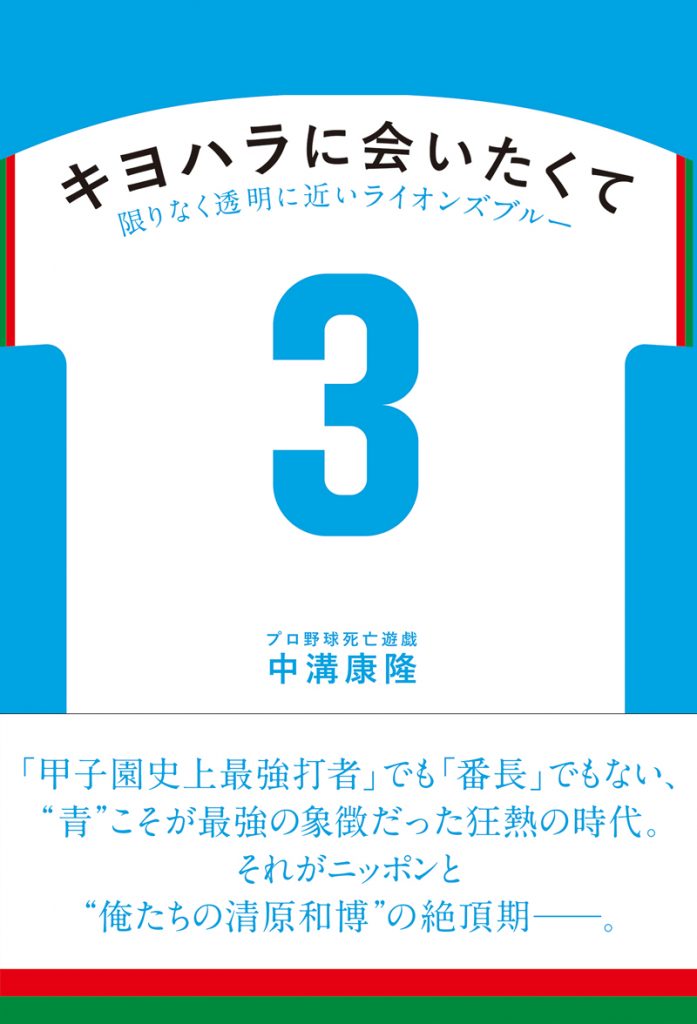
報道陣から「公然と嘘をついたわけですか?」と怒気を含んだ質問が飛ぶと、少しの間を置いて、その記者の方を見据えながら17歳がこう口にするのだ。「まあそう思うなら、思っといてくれたらそれでいいですけど」と。たいしたタマだ。令和の今、一連の映像を見返すと桑田の鉄の精神力に圧倒される。直撃取材してきた記者に対し「どなたですか? 名刺を見せてください」なんて睨み返したこともあったという。雑誌『週刊平凡』85年12月13日号で「蟻が手を這っても泣きだすような子でした」と母親が語る大相撲の新大関・北尾光司とは肝っ玉のデカさが違う。
「中3のときでした。新日本プロレスの試合があって見に行ったら、アントニオ猪木さんに“うちに入らないか”と誘われたんです。ぼくはハルク・ホーガンが大好きだったので、もしその直前に立浪部屋へ入門が決まってなかったらそのままプロレスに進んだかもしれません」なんつってその後の人生を暗示するかのような能天気なカミングアウトをかます新大関を横目に、同号で組まれたKKドラフト特集で、清原の母・弘子さんは夢破れた息子と一緒に大声で泣いたことを明かした。勝手に恋をして、失恋しちゃったんです。あこがれて、ふられて、悔しくて泣いた。『週刊文春』の弘子さん独占手記では「“巨人、巨人”と言っていたのは和博の勝手な片想い。相手が“清原、清原”と言っていたわけではないのですから」と巨人入りの夢がかなうかは半信半疑だったことを認めている。
確かにドラフト前の主役は清原だった。それが20日以降はまさかの巨人単独1位指名で桑田に注目が集中した。目立つのは『週刊ポスト』の「清原を育てられるのはこの人だけ!?
西武監督難産劇と長嶋茂雄」って週刊誌伝統芸の唐突すぎるミスターぶっこみくらいだ。意外なことにジュリアに傷心の清原は、ドラフトからわずか6日後の11月26日に富田林の料亭で西武と初交渉に臨んでいる。
【キヨハラに会いたくて 限りなく透明に近いライオンズブルー】
▼Amazonで購入